わが国の企業経営の現状
1.はじめに-共通な制度としての資本主義と株式会社-
資本主義とは、一般に①自由経済とその下で働く競争原理、②競争にもとづく市場原理、③営利を目的とする民間企業による経済の運営、および④私有財産制度の下で出資者によつ企業の私有、等を特徴とする経済制度である。もちろん、人間が作る制度であるからそれぞれの国の歴史や文化によってさまざまなバリエーションがある。株式会社とは、株式平等原則のもとで均等な内容を持つ株式という権利と引き替えに出資を受ける企業形態で、①法人格、②出資者の有限責任、③株式の自由譲渡性、④所有と業務執行の分離、および⑤株主による所有を共通の特徴とする世界的な制度である(1)。
注1)若杉敬明『新版入門ファイナンス』中央経済社2011年 第2章「資本主義と株式会社制度」
このように、資本主義においては、出資者が企業の所有者であり、出資者が所有に基づいて会社に対する支配権(ガバナンス、コントロール)を有する。株式会社においては株主が出資者であるから、株主が会社の所有者であり、株主が会社を支配できる。ここで支配とは、(a)会社を自ら経営すること、あるいは(b)他者に経営を委ねることである。多数の株主の存在を前提とする株式会社制度においては、後者の(b)が採用され、株主は自ら会社を経営せず、株主総会で取締役を選任し、取締役会に会社の経営を委ねる。ここで、取締役は「株主であることを前提としない」ということが株式会社制度の特徴である。つまり、株主は自らの代理人として第三者を選任し、経営を委ねることになっている。ここにコーポレート・ガバナンス問題の原点がある。つまり、株主は代理人をどのように監督-ガバナンス-し、代理人に株主の意向に沿った経営をさせるかという、エージェンシー問題である(2)。
注2)資本主義を採るわが国は、民間企業の活動により、国民が必要とする財・サービスの生産・流通を行い、その過程において付加価値の生産=所得の創出することを、経済の原則としている。企業形態の中心として会社を制度化し、小規模な事業活動については持株会社として、合名会社、合資会社、合同会社を定め、大規模な事業を行う会社については株式会社を定めている。
エージェンシー問題の解決策として、現代採られている方法は次のガバナンス体制である。株主は、(a)株主に対して忠実で、他のステークホルダーからは独立な取締役を選任し、(b)取締役会は、取締役とは別人を執行役員(経営者)として選任し会社の経営を委ね、(c)独立取締役を中心とする取締役会は株主のガバナンスを代行し、執行役員の経営ぶりの監督に徹するというのが「現代の潮流」である。これを「出資者(株主)と業務執行者(経営者)の分離」あるいは「ガバナンスとマネジメントの分離」という。
2.わが国の資本主義観と株式会社観
会社法は会社の目的が営利であることを前提としているとするのが通説である。営利とは事業を行い、利益を上げてそれを出資者に分配することである。出資者にとっては、当然利益は多いほどよい。株主は、利益を求めて会社に出資を行うと考えるのが自然である。したがって、会社の目的は株主利益の追求であるべきである。ただし、(a)現代の社会はゴーイング・コンサーンを前提としており、かつ(b)株主総会で積極的に議決権行使を行うのは、年金、財団などの分散投資・長期保有を原則とする機関投資家であるので-わが国は先進国の中でも例外的であるが-、企業は長期的な利益を考えるべきであるとされている。このような市場観から、企業の目的は株主価値創造、株主価値最大化とされる。
それに対して、経営者の主たる目的は、現在の地位の安泰と安定的な報酬であると考えられる。しかし、株主価値を創造して行くためには、現代の厳しい競争環境の下では、経営者は絶えず新しい事業機会を開発し、その事業に投資を実行し、利益を実現して行かなければならない。従来の事業にこだわっていては、次々と現れる競争相手に利益を奪われてしまうからである。したがって新しい事業を開発する必要がある。新しい事業にはリスクをともなう。しかし、そのリスクを恐れていては利益を機会は巡ってこない。経営者は、自らの利益と株主の代理人として株主価値創造との間で板挟みになり、可能であるならば、敢えてリスクを取るような経営をしたがらないであろう。しかし、株主は、経営者に対して、リスクを取る経営を望むであろう。もちろん、ただリスクをとれば良いのではなく、株主が望むのはリターンに見合ったリスクでなければならない。かくして、明らかに、株主と経営者とでは利害が反する。経営者に対する何らかの仕組みが必要である。そこで、経営者の報酬を株主の利益と一致させるために、株主の利益と関係の深い業績指標と、経営者の報酬とをリンクさせるという業績連動報酬が多くの国で採用されている。これが、いわば現代企業のベスト・プラクティスである。
私見では、わが国には①企業の目的-営利-に関する社会的認知が株式会社制度とずれている、それに対応して②経営者に対する合理的な動機づけの仕組みがなく、経営の劣化を招いているという問題がある。
以下は、今世紀に入ってからの私の個人的体験、つまり①上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する継続的調査(3)、②上場会社の取締役・監査役の経験、③ミシガン大学ロス・ビジネススクールGlobal MBAプログラムのFaculty Adviserの経験、等々に基づく「日本の経営とガバナンス」論である。ここで指摘するようなことが日本経営を駄目にしてきたのであり、この問題を解決することこそがアベノミクスの課題であると考える。「良質の経営を導く」のがコーポレート・ガバナンスの機能であり目的だからである。
注3)http://www.cg-net.jp/jcgr/survey.html
3.日本社会の問題
日本は資本主義国であるにもかかわらず、資本主義とはいかなる原理・原則に基づくものであるかが理解されていない。さらに、資本主義のもとにおける株式会社についても正しく理解されていない。上述のように、資本主義では、私有財産制度のもと原則として企業は出資者の私有財産であり、企業の所有者は出資者である。したがって、株式会社に対するガバナンスつまり支配権は株主が所有する。これが株主のガバナンスであるそれにもかかわらず、「会社は誰のものか」、「会社は従業員のものである」というような不毛な議論が依然として繰り返されている。
企業の健全な事業活動によりすべてのステークホルダーが恩恵を受ける。ただし、企業がすべてのステークホルダーを尊重(respect)し、資本主義の大原則である市場原理に基づいた取引をおこなう限りである。その意味で企業はみんなの(ための)ものであるが、制度上は株主の私有財産-法律上でなく経済的事態として-であるから、株主が私有財産から最大限の利益を得ようとすることが許される。市場原理が遵守される限り、企業の利益追求が、結局は、すべてのステークホルダーつまり社会の利益に貢献するのである。わが国ではこのことが理解されず、企業が利益を追求することが、社会に広く受け入れられているとは言えない。サラリーマンの人たちも、自分の会社の利益が大事であることは身に染みて分かっているが、株主価値最大化ということには抵抗を感じる人が多い。これはもっともなことである。サラリーマンは、直接の責任としては自分の仕事を一生懸命やれば良いのであり、サラリーマン一人ひとりの仕事を企業の利益につなげるのは経営者の役割だからである。一方で、サラリーマンも公的年金である厚生年金や企業年金を通じて株主である。株主の利益にもう少し敏感になっても良いことも事実であると考える。
株主利益の追求に一生懸命にならなければいけないのは、株主から会社を預かっている経営者である。そうは言っても、経営者自身も自分は株主の代理人であり、株主利益を追求するのが自分の唯一の使命であるとは考えたくないであろう。だからこそガバナンスが必要なのである。経営者の思いとは関係なく、株主利益を追求したくなるような仕組みが必要なのである。これが後述のガバナンス・システムによる経営者に対する動機づけである。
多くの企業がウエブサイトで、経営者の「経営理念」や企業の「行動指針」を掲げ、企業は株主のためのみでなく、社会のために貢献することを謳っている。経営者が自らに対して、そして従業員に対して、自分たちは株主の奴隷ではないことを自らに納得させるためと理解できるのではないだろうか。
最近は日本の経営者も「株主」、「株主利益」ということを、以前に比べれば頻繁に口にするようになったが、経営者から次のような言葉をよく聞く。「株主、株主というけれど、機関投資家には顔がない。そんな株主をなぜ大事にしなければならないのか?」「個人投資家には顔があるけれど、個人株主は買ったり売ったりで定まった顔がない」、こんな状況では株主を大事にできない。株主がそこに期待しているのは基本的には「利益の分配」、そしてそれにともなう「株価の値上がり」である。誰が株主であるか、どんな顔を持っているかは経営者には関係のないことなのである。経営者は株主価値の向上を心がけていれば良いのである。このことも日本の経営者にも一般の人にも理解できないことの一つのようである。
長々と述べてきたが、ここで問題提起しておきたいことは、株主利益に対する社会的認知がないことから、わが国では経営者に対する業績連動報酬に対する理解がないのではないかということである。このことが、日本の企業経営を麻痺させているように実感するからである。
4.リスクをとれない経営
平成20年度年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)-リスクに立ち向かう日本経済-平成20年7月 内閣府も指摘するように、日本の企業はバブル崩壊以降リスクがとれなくなっている(4)。
注4)http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je08/08b02010.html as of 2014/09/14
1980年代まで高度成長のもとで資金不足に悩んできた銀行も企業も、80年代の好況で豊富な内部資金に恵まれ、かつ成長率の低下に伴う資金需要の減少で資金過剰に悩まされた。銀行は貸出先の減少に悩まされたが、企業は資金調達に制約されずに設備投資等ができる自由度を獲得した。企業は、好調な株価を背景に時価発行による資金調達を積極的に行った。金融の国際化で海外からの社債調達ができるようになったことも大きな要因である。企業は高度成長のもとで常に資金調達難に悩まされ、銀行に頭を抑えつけられてきたが、むしろ銀行に対して優位をもてる企業が多数出てきた。多くの企業が銀行から解放されたのである。
持ち慣れないカネを持てるようになった企業は、投資の採算を度外視して投資を行った。企業が、投資利益率(ROI)が資本コストを超えた投資を行えば株主価値を創造するが、資本コストに達しなければ株主価値を破壊する。株式市場がそのことに気付くと株式市場は暴落する。それが1990年以降の株価下落であり、バブルの崩壊である。
1990年以降、多くの企業が不採算投資の処理に追われた。その結果、銀行は不良債権問題に悩まされ、銀行は機能しなくなり日本経済全体が麻痺した。その結果、1990年代以降は「失われた10年」とも「失われた20年」ともよばれている。この経験は日本企業に多くの負の遺産を強いたと思われるが、その最たるものは、「リスクをとれなくなった経営」の定着である。
不況の中で企業の利益つまり株主利益に対する社会の関心が高まったこともあり、経営者は事業の失敗による利益の減少というリスクを極度に恐れている。企業が営利を追求し株主価値を創造するためには、新規の投資をしなければならない。当然、投資には利益が伴うがリスクもともなう。合理的な判断によりリスクをとる勇気がなければ投資はできない。この臆病が日本企業を駄目にしてきたのではないだろうか。
将来に目を向けるならば、アベノミクスの成長戦略は、新規の成長分野を示し企業に新規投資を促す政策である。経営者がリスクを取ることに臆病であっては、アベノミクスの成功はおぼつかない。
5.インセンティブシステムの欠如
株式会社制度を採る国の多くでは、経営者報酬は固定報酬と業績連動報酬との組み合わせであり、かつ後者のウエートが大きいという報酬制度が採られている(*)。
(*) タワーズペリン編『「経営者報酬」の実務詳解』中央経済社 2008年3月
組織における人間行動の心理学的分析の第一人者として知られているビクター・ヴルームの「仕事とモチベーションに関する期待理論」によれば、人間が仕事をするときのモチベーションの強さは、①努力をすれば望ましい結果が得られるという期待、②その結果に対して報奨が与えられるであろうという期待および③報奨は自分にとって望ましいであろうという期待という三つの主観的期待の積として説明することができる。ここでは報奨とその主観的な価値が重要である。
多くの国-とくにアメリカの-のビジネス界では、「優秀な経営者は業績連動報酬制度のもとで結果的に高い報酬を得る」、逆に「高い報酬を得る経営者は優秀な経営者である」という経営者観、価値観が定着している。もちろん、経営者にとっても報酬は高い方が良い。さらにこのような価値観の下では、高い報酬を得れば経営者としてのプライドも満足される。さらに、社会的貢献として報酬の一部を寄付すれば、人間としてさらに高い社会的評価を受ける。
そこで、株主と経営者の利害の不一致を解消するために、①株主利益に連動する企業業績指標にリンクした業績連動報酬や②株主の利益を直接に表す株価と連動する、ストック・オプションなどの株式報酬が活用される。①であれば、業績目標を達成するか否かで、②のストック・オプションであれば株価が権利行使価格を超えるか否かで、経営者報酬は大きく異なることになる。目標管理と業績連動報酬が巧みに組み合わされているわけである。
業績連動報酬の経営者は、ビジネス・リスクを負担し報酬が変動する。ハイリスク=ハイリターンということで、業績連動報酬のもとでは、経営者の報酬は高額になる傾向がある。しかし、業績を伸ばし株価を上昇させていくためには、企業は新規投資をしなければならないのでリスクにチャレンジせざるを得ない。したがって、業績連動報酬は経営者がリスクを取ることを促進する効果があり、株主価値創造に適しているが、他方で、経営者が「過度のリスク」-リターンに見合った以上のリスク-を取る方に走る傾向も無視できない。リターンに見合った以上のリスクということは採算が合わない-投資利益率は資本コストを下回る-投資ということであるから、株主価値を破壊することになる。そこで、最近のアメリカでは、過剰にリスクを取ることを抑制するために、経営者に年間報酬の数倍の金額におよぶ自社株保有を義務づける傾向が顕著になってきている。
わが国でも、最近は役員に業績連動報酬やストック・オプションを付与するケースは多い。上場企業の過半がストック・オプションを採用していると思われるが、固定報酬部分に対する割合はきわめて小さい。経営者の報酬は、事実上、固定報酬であると言っても過言ではない。報酬のリスクが小さいので報酬額も低い。このような環境のもとでは経営者はリスクを取って最大限成長を追求するインセンティブは働かない。これが日本の経営者-とくにサラリーマン経営者(ファミリー企業などのオーナー経営者ではないという意味)-の伝統である。
1980年代半ばまでの、投資機会は豊富にあるのに資金調達が困難であった時代は、このような報酬制度は何の問題も引き起こさなかったが、資金に比して投資機会が少ない状況では、投資に対するインセンティブが働かないということは、致命的な問題ではないだろうか。
このことはまた、経営者の評価が報酬等による客観的基準に基づかないため、経営者の選抜基準が「利益を上げる経営能力」になっていないという重大な問題を引き起こすとともに、後任の指名が現社長の頭の中というブラックボックスで行われ、米国のように取締役会に対する透明性が確保されないと重要な問題につながっている。
6.経営者のリーダーシップ・パターン
2001年以来私は、ミシガン大学ロス・ビジネススクールMBAの1クラスであるGlobal MBA Programのファカルティ・アドバイザーを務めており、毎年30人前後の日本人受験生の入試面接を行っている。原則として企業派遣生が対象のプログラムであるので、企業の大小はあるが、受験生は企業の在籍者である。ロス・ビジネススクールの教育理念の一つは企業リーダーの育成であるので、私には面接で受験生とリーダー観について議論をすることが要請されている。
リーダーシップ論の世界では、リーダーシップには二つの基本要素があることが知られている。一つは業績志向型(P型;Performance type)でありもう一つは組織維持型(M型;Maintenance type)である。当然、経営者のリーダーシップには、当然これら二つの要素が必要であるが、安定した経営環境のもとではM型がより重要であり、変化の激しい環境の下では、将来を見通して企業を導いて行く必要があるので、P型のリーダーシップがより重要である。現代のように厳しい環境のもとでは当然、P型のリーダーシップが強く要請される(5)。
注5) http://www.ritsbagakkai.jp/pdf/414_03.pdf
私が「あなたの身近にリーダーシップのある人がいますか」と質問すると、ほとんどの受験生が「います」と答え、重ねてP型かM型かをたずねると9割以上が「M型」と答える。さらに「あなたはどちらのタイプのリーダーを目指しますか」と質問すると、ほとんど全員が「M型」と答える。
M型は、極論すればみんなが仲良くチームプレーできるような環境作りのリーダーである。現代の変革の時代を乗り切るために、まず必要とされるのは、長期的観点からこれから何をすべきかを示せことができるP型のリーダーシップなのである。つまり、戦略志向的なリーダーシップである。ところが日本ではこのタイプのリーダーシップが不足しているのである(6)。
注6)製造業では、経営者に関して「プロダクト派」「プロセス派」という言葉がよく聞かれる。後者が、既存の製品に関して工程管理等の合理化・化以前などで利益を出してきた会社に貢献してきた経営者を言うのに対して、後者は新製品を生み出して会社の利益に貢献してきた経営者を言う。わが国の経営者の基本的なタイプはプロセス派であることは容易に想像が付く。リーダーシップの型とは直接結び付かないが、経営マインドとしては、プロダクト派がP型、プロセス派がM型に通ずるのではないかと感じている。
7.戦略的経営の欠如
今や技術革新とグローバル競争とで経営環境の変動および競争が厳しくなっている。このような環境のもとで、企業が長期的観点から株主価値創造を続けて行くためには、経営者には①世界経済、自国経済および自産業の将来を見通し、②企業ドメインを確定したのち、③経営理念を確立し、④それをビジョン化するとともに⑤ビジョンを実現する戦略を立案することが不可欠である。しかるに、わが国企業のウエブサイトを見ても、明確・具体的な経営理念の説明は少なく、またビジョンも抽象的であることも多い。同様に、戦略を具体的・詳細に開示している企業も少ない。
社外取締役の経験者に聞くと、取締役会で経営戦略が取り上げられ議論されることはほとんどないということである。私の経験でもほとんど記憶にない。取締役会は、原則として法律で決まった案件を取り上げるだけだからである。戦略の決定や見直しは、株主の利益に大きな影響を与える業務の意思決定に入るはずであるから、会社法の精神に則るならば、当然取締役の議題にされるべきである。困ったことに、会社法には経営戦略というような言葉はないので、通常は取締役会の議案項目に入っていない。したがって、取締役会の議事として上がって来ることはないのである。
企業を訪ね、経営企画部等の経営戦略を担当するはずの部局の管理者にヒアリングしても、経営戦略を議論することはないという答がほとんどである。「戦略を立案しているが取締役会では議論しない」ということではなく、会社の中で戦略に関する検討自体がなされていないのではないだろうか(7)。
注7) http://bizacademy.nikkei.co.jp/management/career/article.aspx?id=MMACz9000027122012
戦略があるにしても次のような問題がある。メーカーの経営者の多くが、自社の技術力には大きな自信を持っている。1980年代に「ジャパン・アズ・ナンバーワン!」と讃え上げられたことが心地よく頭に残っているようである。しかし、その後の20年で製造業もすっかり変質している。多くの分野でITとの融合が進み、製品は見た目には似ているが、製品の本質はすっかり変質しており、似て非なるものになっている。もちろん日本の経営者もその変化を理解しており、一生懸命に対応しようとしている。しかし、その出発点は過去に成功をおさめた技術をベースにした製品である。ところが、たとえば韓国や中国の経営者は、既存の分野における日本の高い技術に追いつくには、莫大な資金と長い時間がかかることを理解しているので、これまで日本の企業が手を付けていない技術にもとづく新しい製品に、あるいは日本企業が手を付けられない(アフリカなどの)マーケットにターゲットを絞っている。日本企業が既存の技術に執着し短い将来しか見通せないのに対して、新興国はより遠い将来のマーケットを見て、新しいドメインを開発しようとしているのである。事業展開の視野に決定的な差があるように思われる。それがまさに戦略の不在となって現れているのではないだろうか。
ミシガン大学ロス・ビジネススクールで勉強している日本人学生によると、最近はどの授業でも日本企業が教材として取り上げられることはほとんどないということである。日本企業について言及されるとすれば、「日本企業には戦略がない」という趣旨のコメントとのことである。1990年代始めまではミシガン大学に行くと、何かについて「日本はどうなっているのか」と聞かれて辟易としたが、最近は声を掛けられることがない。「洟もひっかけない」とはこういうことであろう。
8.経営者の年齢と任期
全上場企業3,550社の現職社長の在任期間は平均7.1年であるが、6年未満が60%、10年以上が25%である(8)。企業規模の小さいファミリー企業においては在任期間が概して長いことを考えると、大企業の平均在任期間は5年程度と推定して良いであろう。しかも、全般的には社長の在任期間は短くなる傾向にあるとのことである。アメリカのCEOも平均は7年強であるが、日本のように任期が半世紀近くに及ぶようなCEOは少ないと言われる(9)。加えて、日本の社長就任年齢の最頻値は59.8歳であるから、平均年齢はさらに高いことになる。他の同僚が定年を迎える頃、役員ということで定年が延長され社長に就任する。なお、アメリカのCEOの平均年齢は56.3歳である。
経済同友会の報告書『経営者のあるべき姿とは-確固たる倫理観に立脚したプロフェッショナリズムとリーダーシップ-』2007はトップの進退のあり方について次のように述べている。
- 株主をはじめとした全てのステークホルダーの厳しい目に常に晒されながら企業価値を高める経営を行っていくためには、経営者はその任期の間は常に“全力投球”することが求められる
- そのため、全力投球が可能な年数と到達するゴール地点(成果イメージ)を自ら設定して、自らに緊張感・アカンタビリティを課すとともに、自らの引き際も明確に描きながら経営に臨むべきであろう。
美辞麗句が並んでいるが、要するに、社長の職をいつまでも続けないで、後進のために潔く辞め、道を譲るべきだと言っているのではないだろうか。このような状況下では経営者はリスクを取ったり、長期的な視野の戦略的な投資をしたりすることなどできないであろう。
注8) http://toyokeizai.net/articles/-/12186 http://yayoiplus.sblo.jp/article/94035930.html
前節で見たとおり、わが国の役員報酬は固定報酬中心であり経営者のリスク・テーキングに対する動機づけはきわめて弱い。これが経営者の戦略的発想を妨げていると思われるが、この任期の短さも、積極的な経営に対する動機づけを弱めていると思われる。しかも、わが国は減点主義であるから失敗は許されない。致命的な失敗をすれば屈辱的な辞任に追い込まれるかも知れない。経営者は短い任期をつつがなく全うするために、果敢にリスクを取って株主価値創造にチャレンジする経営からわが身を遠ざけているものと思われる。
9.経営者の近視眼
1980年代、電気製品を中心にコスト・パフォーマンスの優れた日本企業の製品がアメリカ市場を席巻し、アメリカ企業は四苦八苦の苦境に陥っていた。日本企業が積極的に設備投資をしたのに対し、ROIにこだわるアメリカ企業は設備投資ができないでいた。日本企業の償却資産の平均寿命は4年程度であるのにアメリカ企業のそれは倍であると言われたものである。
アメリカでは1934年の証券法で四半期開示制度が導入された(10)。1980年代の日本は、ジャーナリズムも財界も学者も政治家もこぞって、アメリカは四半期開示があるために短期的利益に目を奪われ、企業が長期的な戦略的投資をできないのだと蔑んだ。私はその頃、東北大学に在籍していたが、経済学部のファイナンスの授業では「日本企業は確かに短期的な視野ではない。だからといって、合理的な長期的な判断に基づいて投資をしているわけではない。何も考えていないのだ」とコメントしていた。「内部留保の資本コストはゼロである」とか、「負債の資本コストは金利である」とかの日本企業の現実を考えれば、合理的な判断があったとは到底考えられないからである。右肩上がりの成長を続けていた日本経済においては、最近お中国企業がそうであったように、企業は何をやっても利益を上げられたのである。
注10) https://www.sec.gov/about/forms/form10-q.pdf
このことは2008年から日本でも四半期開示制度が始まったことにより証明された。2008年前後は、私は数社の社外取締役および社外監査役を務めていたが、この制度が始まって以降、経営陣の最優先関心はこの四半期開示に移ったように見える。もともと戦略的思考が乏しいところに、四半期開示制度が導入されたので、経営陣の関心は一気に短期的利益に移行したように見える。日本の経営者も、同じ状況に置かれればアメリカの経営者と同じことをするのだというのが、私の率直な感想である。
10.経営スキルの欠如
バブル崩壊後も間もなくは、多くの企業が利益を上げたが、逆に国内市場の停滞あるいは縮小で資金の余剰に悩まされた。資金調達難であった過去を思えば贅沢な悩みであるが、何に投資をしようかという苦しみに悲鳴を上げた企業も少なくない。結局、このような企業の多くは、グローバリゼーションの波に乗り、企業買収などで海外展開に乗り出した。しかし、海外M&Aを展開した日本企業の多くは期待した成果を上げていないと言われる(16)。日本企業からの資金注入で息を吹き返し業績を向上させているものの、その成果は買収側の日本企業の業績に反映されないほどわずかなのである。
注11) http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13e085.html
買収した日本企業は、親会社のガバナンスあるいはマネジメントにより、シナジー効果を発揮し、親会社、被買収企業双方の業績を向上させるのが当初の目的だったはずである。しかし、それができていないのである。
私の経験では、海外子会社の視察に行くと、子会社のトップは現代経営理論のコンセプトやモデルで事業を説明する。Five forcesやvalue chainという言葉を用いてかれらの事業展開を説明する。しかし、日本の親会社の中では用語はほとんど聞かれない。これらの理論やモデルがどこまで有効かは別として、現代経営学の標準である、このようなコンセプト、モデル、理論により共通の言語ができ、ビジネス・コミュニケーションが可能になる。アメリカ企業では、このようモデル等はMBAプロトコルと呼ばれ、社内で議論や決定をするときには、「今日はこれとこれのプロトコルで議論しよう」と決めてから、議論に入るそうである。逆に言えば、経営者たる者は、この種のプロトコルをマスターしておかなければならないとのことである。アメリカ企業でのキャリアが長く役員の経験もある友人(ウィンワークス代表取締役社長渡邊邦昭氏)の話では、最低で20ぐらいは要求されるとのことである。
このことから私が実感することは、日本企業には「経営の知」として最低限の経営スキルの蓄積がないということである。社外役員として会社に入って先ず驚くことは、各企業が外部者には理解できない社内用語でコミュニケーションを行っていることである。これはよく聞く話であるが、これでは経営学や他の企業での成果-ベスト・プラクティス-を賢く利用することができないのではないだろうか。
11.国際化されていない経営陣
上述のように、多くの企業が海外のM&Aを行い多国籍化したが、親会社の取締役会に外国人取締役がいる企業はきわめて少ない。これでは海外の企業情報や経済情報をタイムリーかつ適切に取り入れることが出来ず、取締役会の意思決定が偏るのではないだろうか。 同様に女性の取締役がいる会社も多くない。一般的にいうならば、diversityに対する配慮が欠けた経営と言わざるをえないであろう。
12.社外取締役の誤用
最近の日本では「コーポレート・ガバナンス改革といえば社外取締役の導入」との観があり、社外取締役を導入する企業は急増している。
ところで社外取締役の役割は、後述するように二つある。第一は「株主のガバナンス」を実効あるものにすることである。つまり、指名、報酬、監査の各委員会のメンバーになり、それぞれの監督機能を果たすことである。第二は、ガバナンスの観点からは副次的なもので、取締役会において社長を中心に進められる重要な意思決定が適切になされているかを監視することである。また、必要に応じてアドバイスをすることである。多くの場合それなりの経験や専門分野の人が社外取締役として招聘されているのであるから、その経験や専門を活用することは意味のあることである。しかし、ガバナンスという観点からはこれは社外取締役の副次的な利用法であるが、日本の企業では社外取締役の(ガバナンス)以外の意見をありがたがる傾向がある。外部者の専門的知識が必要であるならば、本来、コンサルタントなどを利用すべきである。それをたまたまある分野の人が社外取締役になっているからと言って、その人の意見などを尊重しすぎるのは誤りではないだろうか。
わが国では、社外取締役によりガバナンスの機能は果たされていないと言っても過言ではない。社外取締役が制度化されている委員会設置会社においてもそのようである。そもそも招聘する側の経営者自身が、社外取締役にガバナンスの役割を期待していない。また、社外取締役の二つの役割を正しく理解している社外取締役は少なく、また仮に理解しているにしても、社長の意図をおもんばかり、ガバナンスの改革を進言することはほとんどないからである。結果として、社外取締役の制度はガバナンスの観点からみると正しくは運用されていないのである。これはコーポレート・ガバナンスや取締役会のガバナンスが社会的に理解されたり認知されたりしていないからだと推測する。
13.まとめ
私が気付いてきた日本企業の特徴について私見を述べてきた。これらは相互に関係があり、総合としてリスクをとれない日本経営を実現している。
もちろん、企業によってはエクセレント・マネジメントが見られるが、日本全体としては経営力は脆弱、貧弱であると言わざるをえない。最近のMBA留学希望者には理工系、技術系のプロフェッショナルが多い。私がミシガン大学のMBA入試面接で見た限りでは、かれらが留学を希望する理由を大胆に要約すると次のようになる。「私たち技術者が優れた技術や製品を開発しているのに、わが社の経営者は経営力がないので利益に結びつけてくれない。かくなる上は、私たち技術者が経営の科学を勉強して会社を経営するしかない。」 (以上)
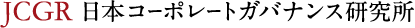
 page top
page top