米国コーポレートガバナンスの歴史
-株式会社誕生とコーポレートガバナンス進化の歴史ー
一般社団法人 日本コーポレートガバナンス研究所
代表理事 若杉 敬明©
無断引用・転載を禁じます
0:前史:株式会社誕生1791年から1900年頃まで
>>アメリカ合衆国(以下米国)では、株式会社の設立と株式市場の誕生は、以下の通りである。
株式会社の設立:
- 米国で株式会社が初めて設立されたのは、1791年に設立された「Bank of the United States(第一合衆国銀行)」であるとされている。
株式市場の誕生:
- 米国で最初の組織的な株式市場は、1792年にニューヨークで誕生した。
- これは、ニューヨークの金融街であるウォール街の24人の仲買人が、同年に「Buttonwood Agreement(ボタンウッド協定)」を締結したことに始まる。
- この協定により、彼らはウォール街のボタンウッドの木の下で取引を行うことを合意し、これが後のニューヨーク証券取引所(NYSE)の礎となった。
補足:
- 実際には、これ以前にも米国では株式会社に似た組織は存在していたが、法的に正式な株式会社として設立されたのは「Bank of the United States」が最初であると一般的に認識されている。
- また、株式市場についても、1792年の「Buttonwood Agreement」以前から非公式な取引は行われていたが、組織的な取引所として確立されたのはこの年であるとされている。
1.19 世紀、米国における株式会社の制度化
19 世紀、米国では各州が制限的な設立認可制度から一般的な法人設立法へと移行するにつれ、法人形態、特に株式会社が制度化された。初期の米国法人は特別な立法認可によって設立されたが、主要州で一般的な法人設立法が制定されたことで、企業の法人設立が容易になった。
(1)初期の法人設立法の主要州
1)ニューヨーク (1811):
ニューヨークは、一般的な法人設立法を可決した最初の州となり、特別な立法行為を必要とせずに企業が法人設立できるようになった。この法律は主に製造会社に使用されましたが、より広範な企業拡大の先例となった。
2)マサチューセッツ (1830 年代~1850 年代):
マサチューセッツは一般的な法人化法を改良し、その適用範囲を製造業だけでなく鉄道、銀行、その他の事業にまで広げた。
3)ニュージャージー (1889 年):
19 世紀後半までに、ニュージャージーは法的優位性を求める大企業を引き付ける非常に柔軟な法人法を制定した最初の州となった。ニュージャージーは持株会社を認め、スタンダード オイルのような企業が信託会社として運営し、複数の事業を統括できるようにした。
4)デラウェア (1899 年):
デラウェアはニュージャージーに倣い、20 世紀初頭に最も法人に優しい州としてニュージャージーを追いた。今日でも、デラウェア州は米国で最も重要な企業法の管轄区域である。これらの変化により株式会社が制度化され、米国では株式会社が大規模事業組織の主流となった。
(2)19 世紀の米国における企業統治
19 世紀の企業統治は、少数のインサイダーの手に大きく集中しており、少数株主や一般投資家に対する法的保護は最小限であった。
1)権力の集中と弱い株主の権利
創業者またはインサイダーによる支配:
多くの企業は、依然として創業家、役員、または少数の大口投資家グループによって支配されていた。株主民主主義は主に形式的なもので、主要な決定はインサイダーによって決定されていた。
2)取締役会は受動的であった:
現代の取締役会とは異なり、19 世紀の取締役会は、企業インサイダー、銀行家、または CEO や主要株主の側近で構成されることが多かった。彼らは独立した監督者というよりは、ゴム印のような役割を担っていた。
3)少数株主の保護が限られている:
小規模投資家は経営陣に異議を唱える余地がほとんどなかった。代理投票はしばしば操作された。開示要件がなかったため、少数株主は利益相反や財務リスクに気付いていないことが多かったのである。
(3)鉄道の役割と金融資本家の台頭
1)鉄道は最初の大規模企業であった:
鉄道は巨額の資本投資を必要とし、最初の大規模な株式公開になった。これらの企業は、プロのマネージャーを擁する企業構造の先駆者であり、所有権と日常的な管理を分離した。
2)銀行家と金融家がガバナンスをコントロール:
投資銀行、特に J.P. モルガン & Co. は、取締役会の任命と企業戦略をコントロールすることが多かった。合併や統合は、会社の幹部ではなく金融家によって計画されることが多かった。
(4)透明性の欠如と利益相反
1)標準化された財務報告がない:
現代の SEC の要件とは異なり、19 世紀の企業には財務諸表を公開したり利益相反を開示したりする義務がなかった。インサイダー取引と株価操作は一般的であり合法であった。
2)自己取引と関連当事者間の取引:
企業の幹部や取締役は、しばしば自己取引を行い、自分の会社や家族に契約を授与していた。
(5)初期の反トラスト規制と企業改革の取り組み
1)独占とトラストの台頭:
スタンダード オイル、US スチール、アメリカン タバコなどの企業はほぼ独占企業に成長し、業界全体を支配した。多くの企業が持ち株会社やトラストを利用して競争を回避した。
2)シャーマン反トラスト法 (1890):
米国政府は、独占の台頭に対応して、反競争的なビジネス慣行を打破することを目的とした最初の主要な反トラスト法を制定した。
《まとめ》
19 世紀には、ニューヨーク、ニュージャージー、デラウェアなどの州で一般的な法人設立法を通じて株式会社が制度化された。しかし、コーポレート ガバナンスは依然として弱く、インサイダーによる統制が集中し、株主の権利は最小限で、財務の透明性も欠如していた。投資銀行と独占的トラストの力が増大したことで、最終的には早期の規制努力が生まれ、20 世紀の現代のコーポレート ガバナンス改革の基盤が築かれた。
Ⅰ.1900年から第2次大戦終了まで
1900年から1945年までの米国企業におけるコーポレート・ガバナンスの状況と歴史は、米国が近代産業経済へと移行する中で、大きく発展した。この時期は、大企業の台頭、規制監督の強化、そして企業界を形作るガバナンス慣行の始まりを特徴づけた。時代を区分して主な特徴を見て行く。
1. 産業成長と統合の時代(1900年~1920年代)
(1)大企業の出現:
1900年代初頭までに、産業の成長により、U.S.スチール、スタンダード・オイル、ゼネラル・モーターズなどの大手企業が台頭した。これらの企業は、鉄鋼、石油、自動車などの主要産業を支配した。この時代には、複合企業や企業連合が設立され、それらはしばしば、少数の有力な経営者や金融業者(例えば、J.P.モルガンやジョン・D・ロックフェラー)によって支配されていた。
(2)権力の集中:
コーポレート・ガバナンスは大幅に中央集権化され、少数の取締役と経営陣が絶大な権力を握っていた。株主の影響力は限定的で、企業が分散した一般株主からの出資をますます受けるようになったため、「オーナー経営者」モデルは衰退し始めた。
(3)規制の欠如
ガバナンスの慣行は、非公式で不透明な部分が多く、少数株主の保護や経営陣の説明責任の確保にはほとんど重点が置かれていなかった。インサイダー取引、市場操作、利益相反は一般的であった。
(4)主な出来事
シャーマン反トラスト法(1890年):以前に可決されていたものの、この時期にはスタンダード・オイル(1911年)のような独占企業の解体や反競争的行為の抑制を目的として積極的に施行された。
2. 1920年代の好況と楽観的な企業
(1)急速な経済成長:
1920年代は「狂騒の20年代」として知られ、前例のない経済成長と株式市場の拡大が見られた。企業への公的投資が急増し、株主基盤の拡大につながった。
(2)コーポレート・ガバナンス基準の低さ:
経営陣が支配的なガバナンス構造が続いた。取締役会は受動的なことが多く、経営陣の追認機関として機能していた。情報開示要件は最小限にとどめられ、財務諸表は標準化されていなかった。
(3)投機的バブル:
経営陣や内部関係者が短期的利益を優先することが多かったため、コーポレート・ガバナンスは投機的行動を抑制することができなかった。
3. 大恐慌とその影響(1929年~1939年)
(1)1929年の株式市場の暴落:
株式市場の崩壊により、広範囲にわたる企業不正、監督の欠如、ガバナンスの失敗が明るみに出た。多くの企業が株価操作により株価を吊り上げており、投資家は壊滅的な損失を被った。
(2)世間の認識の変化:
世間は企業に対して、より大きな説明責任と透明性を求めるようになった。企業幹部は受託者責任よりも個人の富を優先しているとして批判された。
(3)規制改革:
連邦政府はコーポレート・ガバナンスの改善を目的とした画期的な法案を提出した。
1933年証券取引法:投資家を保護するために、企業に対して正確かつ標準化された財務情報の開示を義務付けた。新たに設立された証券取引委員会(SEC)に証券の登録を義務付けた。
1934年証券取引所法:証券取引委員会(SEC)を設立し、証券市場の監督とコンプライアンスの徹底を図った。インサイダー取引や市場操作を防止するための規則を導入した。
(4)企業の財務報告:
監査済財務諸表の提出が義務化され、コーポレート・ガバナンスに外部説明責任が導入された。
4. ニューディール政策後の時代(1930年代~1945年)
(1)独立取締役会の役割の拡大
独立取締役の概念が浸透し始めたが、ほとんどの取締役会は依然として内部者によって支配されていた。主要な財務上の決定の承認や経営陣の業績の監視など、取締役会の責任を明確化する取り組みが始まった。
(2)コーポレート・ガバナンスの制度化
経営陣、取締役会、株主の役割分担が明確化され、ガバナンスがより体系化された。取締役の株主に対する受託者責任などの法理論が強化された。
(3)企業の社会的責任への注目
政策立案者や学者が株主の利益とより広範な社会目標のバランスを模索し始めた。この時期に、企業は公共の信頼の管理者として行動すべきであるという考え方が登場した。
◇1941年-1945年 戦争経済と戦時統治への移行(1941年~1945年):第二次世界大戦中、多くの企業が戦争への支援に重点を置いた。政府との契約や監督が企業の運営に影響を与えた。取締役会は、効率性と国家の利益との整合性を確保する上で重要な役割を果たした。
《まとめ》結論
1900年から1945年までの間に、米国における近代的なコーポレート・ガバナンスの基礎が築かれた。この期間には、主に規制のない、インサイダーが支配するシステムから、連邦政府の規制による説明責任と監督が強化されたシステムへと移行した。SECの設立と財務情報の開示の義務化は画期的な出来事であり、戦後のガバナンス改革への道筋をつけた。
この時代、企業の成長と説明責任のバランスを取ること、そして利害関係者の利益を守ることの重要性が強調された。これは、今日でもガバナンスの実践に影響を与え続けている教訓である。
Ⅱ.第2次大戦終了から2020年まで
1945年から2020年までの米国企業におけるコーポレート・ガバナンスの現状と歴史は、経済の変化、規制の進展、社会の期待の進化によってもたらされた大きな変化を反映している。この期間には、経営者資本主義、株主優先、利害関係者重視のガバナンスの台頭が見られる。
1. 経営者資本主義(1945年~1970年代)
(1)経営者の支配:
第二次世界大戦後、コーポレート・ガバナンスは経営者資本主義の時代となり、企業は所有者ではなく、プロの経営者が実質的な支配権を握るようになった。取締役会は受動的な役割を果たすことが多く、独立した監督者というよりも、CEOの味方として機能していた。
(2)経済成長と安定:
米国は戦後の産業拡大、消費者需要、世界的な優位性により、かつてない経済成長を遂げた。ゼネラルモーターズ、IBM、ゼネラルエレクトリックなどの大企業が、アメリカ資本主義の象徴となった。
1)株主の影響力の限界:
株主は分散しており、企業決定に対する影響力は限られていた。委任状争奪戦はまれで、敵対的買収は、事実上、この期間には存在しなかった。
2)ガバナンスの慣行:
コーポレート・ガバナンスは、安定性と長期的成長の確保に重点を置いていた。「ステークホルダー資本主義」という考え方が登場し、企業は株主の利益と並んで、従業員、顧客、地域社会の利益のバランスを取ることも多くなった。
2. 株主活動主義と金融化の台頭(1970年代~1980年代)
1)経済の停滞:
1970年代には、スタグフレーションやオイルショックなどの経済的課題が生じ、受動的なガバナンスモデルに対する批判が高まった。企業の非効率性や業績不振が投資家の懸念事項となった。
2)株主優先の台頭:
ミルトン・フリードマンなどの経済学者は、企業の第一の目的は株主価値の最大化であると主張し、この概念は広く受け入れられるようになった。
3)敵対的買収の台頭:
1980年代には合併や買収が急増し、業績不振の経営陣を牽制する手段として敵対的買収が用いられるようにななった。カール・アイカーンなどのアクティビスト投資家が有力な存在として現れ、株主への利益還元を優先させるよう取締役会に圧力をかけるようになった。
4)規制の進展:
-証券取引法改正(1975年):
市場の効率性を促進し、情報開示要件を改善するための改革が導入された。
-海外腐敗行為防止法(1977年):
外国公務員への贈賄を禁止し、正確な財務記録の保管を義務付けることで、企業の説明責任を明確化した。
5)ガバナンスの変化:
取締役会に独立取締役が加わるようになったが、CEOの影響力が依然として支配的であることが多かった。機関投資家(例えば、年金基金)がより積極的な姿勢を見せるようになり、株主の活動が企業の意思決定に影響を与えるようになった。
3. コーポレート・ガバナンス改革とスキャンダル(1990年代~2000年代初頭
1)機関投資家と委任状投票:
投資信託や年金基金などの機関投資家の増加により、ガバナンスの改善を求める新たな圧力が生じた。株主は、取締役会における透明性、説明責任、独立性の向上を求めるようになった。
2)企業不祥事:
エンロン(2001年)やワールドコム(2002年)の経営破綻に代表されるガバナンスの重大な失敗により、不正行為や利益相反、取締役会の監督機能の弱さが広く明らかになった。これらのスキャンダルにより、コーポレート・ガバナンスに対する社会の信頼は大きく損なわれた。
3)規制改革:
-サーベンス・オクスリー法(2002年):
企業不祥事への対応として制定されたこの法律は、以下のような重要な改革を導入した。CEOおよびCFOは財務諸表の正確性を証明することが義務付けられた。監査委員会は独立取締役のみで構成されることが義務付けられた。また、内部統制と内部告発者の保護が強化されました。
4)役員報酬への注目:
1990年代と2000年代には、企業業績と関連性がないとして批判されることの多かった役員報酬への監視が強化された。
5)ガバナンス慣行:
取締役会はより専門化され、独立取締役が経営陣の監督においてより積極的な役割を果たすようになった。株主の権利は強化され、決議案の提案や役員報酬方針への影響力などが認められるようになった。
4. ESGとステークホルダー資本主義の時代(2010年代~2020年代)
1)環境、社会、ガバナンス(ESG)問題への注目:
ESGへの配慮が注目されるようになり、投資家やステークホルダーは、気候変動、多様性、社会的責任などの問題について説明責任を求めるようになった。企業は、ESG目標を長期的な戦略に組み込むようになった。
2)ステークホルダー・ガバナンスへのシフト:
ビジネス・ラウンドテーブルが2019年に発表した「企業の目的」に関する声明は、株主優先主義からステークホルダー資本主義への転換を意味するものでしあった。この声明では、顧客、従業員、サプライヤー、地域社会、株主に対して価値を提供することの重要性が強調された。
3)機関投資家の役割の拡大:
ブラックロックやバンガードなどの大手機関投資家は、その影響力を利用して、持続可能な事業慣行とガバナンス基準の改善を推進した。
4)技術的混乱:
テクノロジーの進歩によりコーポレート・ガバナンスが変化し、より高い透明性、データ分析、株主とのコミュニケーションが可能になった。
5)規制の変化:
-ドッド・フランク法(2010年):
2008年の金融危機を受けて改革が導入された。株主による経営陣の報酬に関する投票が義務付けられた。また、システミック・リスクを低減するために、金融機関に対するより厳格な監督が課された。
6)ガバナンスの実践:
取締役会は、テクノロジー、サイバーセキュリティ、ESGなどの分野における専門知識を備えた、より多様で有能な人材で構成されるようになった。株主との関わりも深まり、企業は投資家向け説明会を開催し、自社の戦略を積極的に発信するようになった。
<まとめ>1945年から2020年までの主な傾向
1)経営者資本主義から株主資本主義への移行:
焦点は経営管理から株主価値の最大化へと移り、さらに最近では、複数の利害関係者の利害のバランスを取ることに移行した。
2)取締役会の強化:
取締役会は受動的な機関から能動的な監視機関へと進化し、独立性、多様性、説明責任が重視されるようになった。
3)規制および法改正:
サーベンス・オクスリー法やドッド・フランク法などの重要な法律が制定され、ガバナンスの慣行が再構築され、透明性が向上した。
4)アクティビズムとESGの台頭:
株主アクティビズムが、環境問題や社会問題への関心の高まりと相まって、ガバナンスの進化の主な推進要因となった。
《まとめ》
1945年から2020年にかけて、米国のコーポレート・ガバナンスは経営陣が支配する体制から、株主、アクティビスト、その他の利害関係者が影響を及ぼす体制へと進化した。 規制改革はガバナンスの失敗に対処し、社会の変化は企業に利益創出と社会および環境に対する責任のバランスを取ることを迫った。 2020年までに、コーポレート・ガバナンスはよりダイナミックで透明性が高く、包括的なアプローチを反映するようになり、21世紀における継続的な進化の基盤が整った。
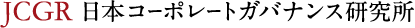
 page top
page top