日本コーポレートガバナンス研究所
理事長 若杉 敬明
企業は、人々が社会生活をする上で必要な衣食住などの財やサービス(以下単に製品という)を提供するともにそこに働く従業員に給料という収入をもたらしてくれる。企業活動は社会にとって重要であるので、社会にはさまざまな企業があることが望ましい。自由主義をベースとする資本主義国では、私企業(=民間企業)に営利活動を認めることにより、人々が必要とする製品が社会に行き渡ることが期待されている。営利が成立しない製品については公企業が生産・流通を担う。
1.会社法と会社の目的
わが国では私企業の代表的な形態として会社法により会社が規定されている。ここでは会社とは、法人格を認められた、出資者を社員とする社団で会社の目的は営利であるとされている。営利とは事業を行うことにより利益を上げそれを出資者に分配することである。出資者は利益の分配を受けることを目的として出資をするのであり、利益は多いほど望ましいので、会社は自ずとより多くの利益を目指すことになる。出資者が会社の存続を望むときには、短期的な利益ではなく長期的な観点からより多くの利益を望むであろう。このことを会社の目的は長期的利益の最大化あるいは単に利益の最大化であるという。
2.株式会社と持分会社
わが国の会社法は、株式という均一な小単位に分割された権利(議決権、利益配当請求権、残余財産分配請求権)の所有と引き換えに出資を得る株式会社と、株式を発行せず出資者は持分と呼ばれる出資割合を所有する持分会社とを定めている。小規模な事業を前提とする持分会社には、社員が、有限責任社員のみの合同会社、無限責任社員のみの合名会社、および有限責任社員と無限責任社員とで構成される合資会社の三形態がある。持分会社では、出資者が自ら会社を経営するのが原則である。他方、大規模な事業を前提とする株式会社においては有限責任社員のみであり、出資者自らが会社の経営に従事することを前提としていない。
3.株式会社のガバナンス問題
株式会社においては、株主は取締役を選任して取締役会に経営を委ね、自らは経営に関与しない。出資者として株式会社のオーナ-であり、会社に対するガバナンスを有するが、経営そのものにはタッチしない。もちろん、株主も取締役や経営者になることができるが、株主や取締役会が、経営者としての認知する場合だけである。 株式会社も会社であるから目的は営利であり、利益は多い方が望ましいので株主は利益最大化―現代では長期的な利益すなわち株主価値の最大化―のために経営者がベストを尽くすことを期待していることを、経営者は理解している。しかし、経営者は会社の中にいる内部者であるが、株主は外部者であり、経営者が行っている経営のすべてを見ることができない。そこに盲点があり、経営者は株主の立場に立ち株主価値最大化のためにベストを尽くすとは限らない。それに、経営者の個人的な目的は、経営者としての名声であったり自らの報酬であったりして必ずしも株主価値の最大化ではないであろう。 実際、経営者の不祥事や非効率な経営が長年にわたり問題になってきた。その結果、株主価値を損なうばかりでなく、会社の倒産などで他のステークホルダーの利益を害してきた。そこで、経営者を営利に邁進させるための仕組みや機能が必要になる。それがコーポレートガバナンスである。
4.会社法のガバナンス規整
「株式会社の経営は、株主が自らするのではなく、株主総会で取締役を選任し、会社および経営を取締役に委ねる」という仕組みを決めた会社法は、株式会社の出資者かつ所有者である株主の利益を守るために株主のガバナンスが効果的に働くように、ガバナンス規整を敷いている。
会社は法人として人格が認められており法律的な行為をなすことができるが、あくまでも法人は形式的な存在であり、自然人や自然人による会議体などの機関がなければ、意思決定もその執行もできない。現在の日本では機関のあり方として、監査役会設置会社、指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社の三つが認められているが、伝統的な監査役会設置会社を例にとって、どのようにガバナンス規整がなされているか見てみよう。
注)日経新聞(2019/7/13)によると2019年6月末現在、全上場企業3739社のうち監査等委員会設置会社1027社、監査役会設置会社2634社、指名委員会等設置会社78社(2020年6月13日現在の上場会社数は3827社)
5.監査役会設置会社のガバナンス体制
株主総会において株主は、基本的事項(定款の変更、事業譲渡、合併等の組織再編行為、解散等)についてのみ意思決定し、それ以外の会社経営に関する事項の決定と執行は取締役を選任し取締役会に委ねる。
株主総会は取締役の選任・解任により取締役を監督する。これがコーポレートガバナンスの枠組みにおける株主のガバナンスである。
取締役は、全員で取締役会を構成し、会社の業務に関する意思決定をするとともに代表取締役・業務執行取締役を選定する。ここで業務とは会社の目的である営利に大きく企業の活動を指す。
代表取締役は業務意思決定を執行し、対外的には会社を代表する。業務執行取締役は代表取締役の業務意思決定執行を補佐する。
取締役会は代表取締役および業務執行取締役の業務執行を監督する。監督とは、営利に向けて経営の適正化を図るため、業務執行の体制およびその妥当性を確認することである。(平易に言えば、現在の経営が適正であると認め現経営陣の継続を容認するか、あるいは経営を変えるために解任すべきかを判断することである。)
監査役・監査役会は、➀ 取締役の職務の執行を監査する業務監査(適法性監査)と➁ 計算書類等の監査を行う会計監査の2つの権限を有する。監査役会設置会社のガバナンス体制は世界のガバナンスと比較すると次のように特殊である。
わが国では明治23年に初めて商法が制定された。その後、明治32年に新しい商法が公布されたので初めての商法は旧商法と呼ばれるが、株式会社のガバナンス体制は新しい商法でも引き継がれ、昭和25年商法改正により英米流の取締役会制度が導入されるまで続いた。
旧商法においては、株式会社の運営体制として、基本的意思決定を行う株主総会、業務執行を行う取締役、監督を行う監査役の3機関置かれた。監査役に与えられた権限は、経営監督権限と会計監査権限である。昭和25年の商法改正により、経営監督は取締役会による自己監査が原則になり、監査役の職務は会計監査が基本となった。監査役の権限は大きく縮小されたわけである。しかし、証券取引法(現在の金融商品取引法)との整合性を図るために、1974年の商法改正により監査役に再度業務監査権限が付与された。これにより、業務執行に対する取締役会の監督権限と監査役の監督権限という二重性が固定され現在に至っている。かし、取締役会の自己監査が形骸化していったことから、その後、粉飾決算や企業不祥事などが社会的問題になる度に、監査役の権限強化と地位強化(独立性の確保)とで対応がなされてきたが実効が上がらなかった。ついに2002年、英米型の三委員会制を取り入れた委員会等設置会社が導入され、監査役会設置会社との選択制が布かれた。
6.英米流の取締役会制度
英米型の取締役会は次のような仕組みになっている。➀株主総会で取締役を選任する ➁取締役は取締役会を構成し業務に関わる重要な意思決定を行う ③取締役会は業務執行役員を選任し業務決定の執行を委任する ④取締役会は業務執行役員および業務執行を監督する ⑤業務執行役員のトップであるCEOから株主への会計報告を外部監査人が監査する。
株主総会における取締役の選任を「株主のガバナンス」というのに対して、取締役会の業務執行役員に対する監督を「取締役会のガバナンス」という。同じくガバナンスと言っても、取締役のガバナンスは株主のガバナンスよりやるべきことが沢山ある。英米の会社も利益を株主に分配することを最終目的としているので、会社の目的は営利であるということができる。したがって、取締役会の監督の対象は営利追求の業務執行体制を整備し、業務執行役員を営利に向けて邁進させることである。
しかし、英米の企業においても、現在の日本企業のように、取締役が業務執行役員を兼務しており、取締役会のガバナンスは問題の多い自己監督であった。その結果、1980年代以降、企業経営は、会計の虚偽報告や経営者の不祥事あるいは経営業績低迷など、株主にとっても社会にとっても甚大な影響を及ぼす問題を惹き起してきた。。
株式会社制度上、健全な経営を実現するのは、経営者すなわち業務執行役員を監督する立場にある取締役会、すなわち取締役会の責任である。このような法律上の建て付けのもと、取締役会はガバナンスの実務として何をすべきかが問題とされた。それを解決しようとしたのが、英国におけるカドベリー委員会(1992)以降の諸委員会活動―グリーンベリー委員会報告(1995)、ハンペル委員会報告(1998)、ターンバル委員会報告(1999)、スミス委員会報告(2003)、タイソン委員会報告(2003)等―である。2003年、それらを総合する「改訂コーポレートガバナンス≓規範」(新統合規範である)である。さらに内部統制を統合した「改訂コーポレートガバナンス統合規範」(2008)に集大成された。これらの委員会には経営者協会も参加しており経営者協会も合意したものである。さらに、ロンドン証券取引所もこれの研究会活動に参加しており、新たに報告書に盛り込まれたことは、取引所の樹上規則として実効化された。後に日も導入した、Comply or Explain“もその一つである。
アメリカではそのような委員会活動は行われず、これらの影響を受けつつもっぱら実務が先行した。それが、具現化したのがエンロン事件後のニューヨーク証券取引所の上場ガイドラインである。次にそれを見ていくこととしよう。
7.コーポレートガバナンスのベストプラクティス
(1)ガバナンスとマネジメントの分離と独立取締役
多くの国の会社法において、取締役会は伝統的に、取締役の中からCEOを始めとする業務執行役員つまり業務執行取締役を選定していた。この制度の下で、取締役会は業務執行取締役の業務執行を監督することになっていた。つまり監督を行う取締役会と監督の対象である業務執行取締役とは同一人物である。これでは監督は名ばかりで形骸化してしまう。20世紀後半のグローバリゼーションという大競争の環境の下で、監督を実効化するために取締役は業務執行役員を兼ねないという「ガバナンスとマネジメントの分離」という考え方が育ってきた。取締役会は業務つまり営利に関する重要な意思決定を行うので、会社の事業に詳しい社内取締役も取締役会に入っていることも不可欠である。そこで、最低限少数の社内取締役も含むが、各ステークホルダーから独立で、かつ株主の観点から経営者およびその経営を監督できる社外取締役、つまり社外独立取締役が大多数を占める取締役会が、世界的には現代企業の主流になりつつある。
(2)指名・報酬・監査の三委員会による経営監督
これら三つの委員会はガバナンスの基本委員会である。そのメンバーは独立社外取締役中心に構成される。ニューヨーク証券取引所(NYSE)は全員が独立取締役であることを要求している。
指名委員会: CEO以下の業務執行役員を選任する-あるいは業績を上げられないと判断されれば解任するのは、取締役会の任務である。したがって、それに相応しい能力を備えた独立取締役が不可欠である。取締役会から権限委譲され、あるいは事実上株主総会に提出する取締役候補者のリストを作成するのが指名委員会である。
しかし、誰が社内取締役として相応しいか-通常はCEOやCFO-は、社外取締役を中心とする指名委員会には判断できない。そこで、社内人材のデータベースを持つHR部門(Human Resources Division)の助けを借りざるを得ない。また、社外独立取締役を選任する場合も、HR部門や人材コンサルタントの協力が不可欠である。指名委員会は専門家の協力があって初めて機能を発揮できる。逆に言えば、専門家の知恵を活用できる人材であれば、社外取締役でも指名委員会委員の職責を果たせるのである。指名委員会は第一に社内のHRM部門があって初めて機能を果たせるのである。
取締役会の下には、次に見るように報酬委員会も監査委員会もある。ニューヨーク証券取引所(NYSE)のコーポレートガバナンスガイドラインは、それら委員会の委員長および委員である取締役を決めることも指名委員会に求めている。その他のガバナンスに関連する委員会の設立・廃止および委員・委員長の決定についても同様である。したがって、指名委員会は会社のガバナンス体制の管理を掌握している。そこでNYSEの上場規則は、指名委員会を単に指名委員会と呼ばずに、Nominating and Corporate Governance Committeeと名付けている。指名委員会の委員長である独立社外取締役はガバナンスの責任者として、すべての独立社外取締役の頂点であるとされる。ここでもHRM部門や人材コンサルタントの助けを借りざるを得ないことは言うまでもない。
報酬委員会:どんなに優秀な人材がCEOや業務執行役員に選任されても、営利に向けて動機づけられていなければ、その能力を発揮できない。動機づけのインセンティブは個人によって異なるかも知れないが、ほとんどの人に共通なのは金銭つまり報酬である。昇進も重要なインセンティブであるが、会社の頂点に到達してCEOやCFOにはもはや昇進の余地がない。高額の報酬を得る経営者は優秀な経営者であるとされる社会的な風潮があれば、優秀な業績を上げ高額の報酬を得ることは、経営者のプライドや自己実現の欲求を満足させる。インセンティブ報酬として利用されるのは株主の利益と相関指標とリンクした報酬である。株式報酬をはじめとする業績連動報酬である。このことは業務執行役員が、株主と共通の利害関係に立つということで、経営者報酬と株主利益の一体化と呼ばれる。業績連動報酬においては、業績の目標が報酬制度に組み込まれ、目標をオーバーするほど高い報酬が得られ、逆に目標に達しないとただ働きになるようなルールが組み込まれるのが普通である。経営者が、これこれが会社の目標であると明言すると、それを、それを達成できなかったときに訴えられる訴訟リスクがあるので、暗黙裡に目標を埋め込むという意味も持っている。
業務執行役員の報酬設計においては、事業と業績指標の関係や企業業績と株価の関係などについて会社に固有の専門的な能力が必要である。したがって、業務執行役員の業績連動報酬の設計は社外取締役のみで出来ることではない。ここで社内の報酬設計部門や社外お報酬コンサルタントのサポートが必要である。繰り返しになるが、インセンティブ報酬について一定の理解を持っていれば、社外取締役にも務まるのである。むしろ中途半端に社内事情に通じている人材より、社外の独立な人材の方が望ましいと言える。
監査委員会:経営者は事業を遂行し営利を追求して行くとともに、その過程および結果を株主に報告しなければならない。そのために、最高経営責任者であるCEOが知っておくべきことが三つある。第一は社内の各部署で職務が効率的に遂行されていること、第二に社内の各部署において法律、社内・社会のルールなど守るべきことが守られていること、つまりコンプライアンスが確保されていること、そして第三に、株主から与った財産(出資)の状態、およびその財産を用いて事業を行った結果の利益である。経営者はこれらを毎期株主に年次報告として知らせなければならない。これらを確保するための社内ルールの総体が内部統制であるが、ルールがあるからと言って守られるとは限らない。ルールが守られているか否かをチェックする作業が必要である。ひとつは、外部の独立な機関による財務報告の正確性の検証―会計監査―である。もう一つが、内部でルールが守られているかを検査する内部監査である。会計監査や内部監査が適正に行われるための前提は、会計監査人の独立性および内部監査人の独立性である。現代企業においては、独立性の検証が、監査委員会の基本的な役割であるとされている。
CEOが把握しておくべき3事項が適正に確保されていなことは、企業の利益を脅かす理数要因である。これらを確保するためには監査が必要であるが、監査委員会自体が監査をする必要はない。監査委委員会は内部監査人および外部監査人の独立性を検証し、内部監査および外部監査が適正に行われており、CEOの三事項が確保されていることを保証できる。監査委員会も、内部監査というマネジメント一機能と外部監査という専門家のサポートを適切に確保すれば良いのである。したがって、社外独立取締役にも務まるし、逆に社外独立取締役こそそのような機能に相応しいのである。
(3)むすびに
指名、報酬、監査の機能により、経営のトップであるCEOから効率的で健全な経営を引き出すのが取締役会のガバナンスである。取締役会のリード役が社外独立取締役である。ガバナンスは、業務の執行に直接関わることではないので、社外の独立取締役にも果たすことができる、否、厳しくその職責を果たすためにこそ、独立な社外取締役こそ望ましいとするのが、現代のコーポレートガバナンスのベスト・プラクティスの根底にある思想である。
ここで大事なことは、ガバナンスとマネジメントは一対であるということである。上に見たようにガバナンスは、マネジメントの協力があってこそ機能するのである。他方、健全なガバナンスの下でこそ、マネジメントはその力を発揮できるのである。残念ながら全体としてみると日本の経営は目的志向の合理的・科学的経営という観点からは貧弱である。政府も企業も学界も同様である。ガバナンス改革はガバナンス、ガバナンスとお題目を唱えているだけでは進まない。同時に、マネジメント力を高める施策が必要である。ガバナンス改革を唱えている政府はそれにもコミットする必要があることを自覚すべきである。(以上)
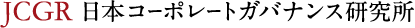
 page top
page top