一般社団法人日本コーポレートガバナンス研究所 代表理事 若杉 敬明
はじめに
わが国では、株式会社のガバナンス体制として、会社法の現在は、監査役会設置会社、締め委員会等設置会社および監査等委員会設置会社の三つを選択の対象としている。フランスでは、ドイツ流の二層型ガバナンス体制と英米流の一層型ガバナンス体制の二層型の選択制となっているが、このような法制は極めてまれである。ところが日本では、三体制の中からの選択制であり、しかも一つの体制から他の体制に自由に移行することができるという、極めて珍しい制度である。この経緯を整理したいと考えていたところ、獨協大学法学部高橋 均教授の「監査等委員会設置会社をめぐる現状と今後の課題」という論文に遭遇した。この論部の展開に大いに賛同するところがあるので、この論文の前半部分の論旨を私の私見を交えつつ紹介する。その意味では忠実な紹介あるいは要約ではない。
明治時代の半ばに商法が公布されて以来、株式会社のガバナンスは監査役が担ってきたが、1950年に英米流の取締役会が導入されると、取締役会の監督機能に取って代わられ、監査役の機能は会計検査機能のみに縮小された。しかし、大会社の粉飾決算が問題になる度に監査役の地位向上によりガバナンスの強化が図られてきた。わが国の監査役制度は、第二次大戦後に限っても長い歴史を有しており、「上場会社等における戦後の機関に関する改正の歴史の相当部分は、監査役制度強化の歴史」であると言える。監査役の地位の強化が図られてきたにもかかわらず、法の期待に反して形骸化しているとの評価が強かった。第一の根拠は、監査役に対する人事権の問題である。監査役の選任は株主総会で行われるが、株主総会への選任議案について、取締役は監査役(会)の同意を得なければならない。しかし、「監査役の人事権が事実上、取締役会ひいては社長に掌握されている限り十分に機能しえない」との批判が強かった。監査役は、取締役会での意見陳述義務があるが議決権を有していないので、代表取締役の選定・解職の賛否に参画することができず、結局は代表取締役が決める監査役の人事案に従わざるをえない。
第二の根拠は、監査役の監査権限の範囲の問題である。学界では、伝統的に監査役の職務範囲は適法性監査権限に限定され、妥当性監査権限までは及ばないというのが多数説あった。企業経営においては妥当性の問題に直面するのが圧倒的に多いので、当然、、適法性監査権限に限られていては、監査役の活動範囲は限定されざるをえない。近年においては、監査役監査報告の記載事項として、内部統制システムの基本方針、M&Aに対する監査役の意見等々記載することになっていることから、監査役の権限は、現実には適法性監査に限定されていないとされている。
2002年商法改正による選択制導入と問題点
長い歴史がある監査役制度に関して、コーポレートガバナンスの観点から制度上の強化が図られてきたが、監査役制度は上述のような根本的な問題をはらんでいた。法務省は英米流の取締役会制度に替えようと委員会等設置会社の導入を図ったが、経済界の反対で監査役会設置会社の制度は残しつつ、委員会等設置会社を新たに創設することになり、選択制で落ち着いた。
委員会等設置会社とは、経営と執行の分離を図りつつ、社外取締役が過半数を構成する指名委員会・報酬委員会・監査委員会の三つの委員会の設置を義務付けた英米モデルのコーポレートガバナンス体制である。監査役には取締役会における議決権がないとの批判に対して、監査役の代替となる監査委員には取締役監査委員として取締役が就くことになった。取締役監査委員は取締役であるから、取締役会での決議に関して議決権があり、通常の経営の意思決定の賛否にとどまらず、代表執行役の選定・解職にも参加することが可能になった。さらに、監査役は適法性監査に限定されるとの論点に関しても、取締役であるから当然妥当性監査も職務範囲である。しかし、監査委員は取締役であり、取締役会での多数決に服する必要があるので、監査役制度の大きな特徴である独任制は適用されない。なお、取締役として内部監査部門等を指揮・命令することにより監査の実効性を確保することが可能であるので、常勤の監査委員は義務付けられなかった。一方、監査役は、取締役とは別の議題・議案として株主総会で選任されるのに対して、監査委員は指名委員会で決定した取締役の候補者を株主総会で選任した上で、取締役会が監査委員を選定する手続きとなっている。
新しい期待を担った、世界スタンダードの委員会等設置であったが、委員会等設置会社に移行した会社数は、多い時でも約150社程度にとどまり、その後は監査役会設置会社に戻る会社もあるなど、現時点では70社前後となっている。指名委員会等の三委員会の権限が英米の委員会よりも強く、委員会での決定は取締役会でも覆すことができないこと、代表取締役としては、職務を遂行する上での権限行使の源である取締役の人事権と報酬決定権のイニシアティブを社外取締役に持たせることに抵抗感があったためと言われている。
当時の立案担当者は、委員会等設置会社制度の創設は、適切な企業統治を実現するための機関の在り方について、会社の選択の幅を増やす趣旨であると明言していた。つまり、監査役会設置会社と委員会等設置会社との制度間競争を意図していたのである。そのために、取締役と執行役を分離して取締役会の独立性を担保することが要である委員会等設置会社において、監査役会設置会社と同様に取締役が執行役を兼ねることまで容認した。しかし、圧倒的に多数の会社が監査役会設置会社に留まっている状況下では、制度間競争の果たせなかったわけである。
- 監査等委員会設置会社創設の背景と特徴
ほとんどの会社が監査役会設置会社に留まった中で、監査役制度と制度間競争になり得るガバナンス体制が模索されました。その結果、新たに創設されたのが監査等委員会設置会社である。監査等委員会設置会社は、指名委員会等設置会社で必置の指名委員会と報酬委員会とを義務付けずに、監査委員会に相当する委員会のみを残した制度設計となっている。監査等委員会設置会社の導入に併せて、三委員会が必置の会社形態を「指名委員会等設置会社」と改称するとともに、新設の会社の監査担当取締役会委員会を、指名委員会等設置会社の監査委員会と区別するために、監査等委員会した。
指名委員会等設置会社においては、社外取締役に取締役の指名や報酬決定のイニシアティブを持たせたことが抵抗感を招いたということで指名委員会と報酬委員会は置かずに、監査等委員会にそれらの委員会を兼ねさせることにした。その意味では、指名委員会等設置会社の特徴も活かしている点で、監査役会設置会社と指名委員会等設置会社との中間的な位置付けと言える。
すなわち、第一の特徴としては、監査委員と同様に、取締役の職務執行を監査する監査等委員は取締役である。それゆえ、取締役会で議決権があり、かつ執行部門である内部監査部門等に対して指揮・命令権を持っている点も監査委員と同様です。
第二の特徴としては、指名委員会や報酬委員会の設置が省かれた代替措置として、監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任、及び報酬等に対して、株主総会において監査等委員会の意見を述べることができる。業務執行取締役の行為を評価した上で、その評価の結果として取締役の人事や報酬に関する意見陳述を行うことによって、監督機能を持たせるとの立法趣旨の説明から、監査等委員会設置会社の「等」は「監督」を意味すると解釈される。
第三の特徴として、監査等委員会設置会社の業務執行取締役の任期が1年間であるのに対して、監査等委員は2年となっている。指名委員会等設置会社の取締役の任期は全て1年であるが、監査等委員会設置会社の取締役監査等委員会委員の任期は、監査役会設置会社の監査役の任期と同様に、業務執行取締役の任期の2倍となっている。任期が業務執行取締役の任期より長いことによって、監査等委員の独立性を担保するためというのが立法趣旨である。
第四の特徴は、監査等委員以外の取締役の利益相反取引に関するものである。監査等委員会の事前承認を得た場合には、監査等委員以外の取締役の利益相反取引により会社に損害が生じた場合でも、当該取締役の任務懈怠の推定が排除される。
このような特徴に加えて、監査役会設置会社においても社外取締役の複数設置義務の要請が高まっている中で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する企業が急増した。そして2019年12月11日公布の会社法の一部を改正する法律により、監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社と同様に、社外取締役の設置義務が施行された。このような事情が監査等委員会設置会社への移行が急速に行われたいる背景である。
原典:獨協大学 法学部教授 高橋 均「「監査等委員会設置会社をめぐる現状と今後の課題」
https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-01-02
2022年2月23日2:15PM
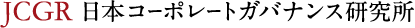
 page top
page top